|
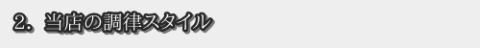
さて、ここからはウィーンの巨匠ピアニストであるイェルク・デームス氏が教えてくださった次の4つの事柄をもとに、
私共が行っておりますピアノ調整・調律について少し掘り下げてお話したいと思います。
『 クラシックにおいて作曲者はピアノ曲を次の4つのことを想定して創ります 』
① 人の声の代わりに歌として
② オーケストラを表現する
③ 室内楽を表現する
④ ピアノという楽器の為
- イェルク・デームス -
多くの曲を聴くと、確かに①のとおり、シューベルトのピアノ曲には歌詞が付いてるように聞こえ、
プロコフィエフやスクリャービンのピアノ曲を聴くと、②のとおり金管楽器が表現されている部分を多く感じます。
モーツァルトやベートーヴェンのピアノ曲は、②③のとおりオーケストラや室内楽を髣髴とさせます。
このように、ピアノという1台の楽器で、上記の4要素を表現することが本来のピアノ曲の目的ではありますが、
そのためにはまずこれら4要素を表現可能にするためのピアノ調整・調律が施されたピアノで演奏することが大前提となります。
そこで、ピアノ調整・調律において、大きく分けて2つの事柄が重要となります。
まず第一に、ピアノが正しく歌えるように調整・調律されていること。
次に、ピアノが伸びのある音色で響かせることができるよう調整・調律されていることです。
しかしながら、実はここに、日本のピアノ調律技術では越えることのできない壁が存在しているのです。
歌い方について、日本と西洋の伝統は大きく異なります。
日本では声帯を中心とした喉を締め付けた歌い方が基本で、浪曲や浪花節などが判りやすい例です。
一方西洋では、喉をリラックスさせた柔らかい声を気持ちよく会場に響かせる歌い方が基本で、
喉だけでなく身体全体を使います。
これは、ピアノ調律にも大きく関わってきます。
日本で行われている一般的な調律では、鳴った瞬間の音(アタック音)は「パンー」と歯切れよく鳴ります。
ところが伸びた後の音を聞くと、弱く弾いても強く弾いても「ンー」や「エー」としか伸びません。
アタックの音色は「ポン」と柔らかくしたり、「カン」と硬めにしたり変化をつけることはできるのですが、
言語で言う子音が変化しているだけで、母音は「ンー」のまま変化しません。
音の形をみてみると、鳴った瞬間の音をピークに次の瞬間には音量が落ち、心電図の波型のようになります。
一方、ヨーロッパで行われている調律では、アタック音の後もさらに声が伸びていき、
鳴った後の音を聴くと、「アー」と開放的な気持ちの良い響きとして聞こえます。
音の形も前者とは異なり、上へ上へと上昇していく形となります。
私は、以前は器楽曲ばかりを聞いており、歌曲があまり好きではありませんでした。
ところが、初めてウィーンを訪れた時、本場のオペラに接してはじめて人の声の素晴らしさに感動し、
人の声は何にもまさる最高の楽器なのだと実感しました。
人の心に響く、気持ちの良い声の秘訣は、喉を自然に開いた発声にあるのではないかと思います。
ドイツの歌曲を歌う時には、浪曲浪花節の歌い方ではなく、当然西洋の歌唱方法で歌います。
同様に、西洋音楽を奏でるピアノには、
やはりヨーロッパの伝統に基づいたピアノ調整・調律を施すのが当然であると思うのです。

次に、音色についても、日本と西洋では大きな違いがあります。
実はこのことも、両者のピアノ調律の違いに大きく関係しています。
日本の調律では、一見純粋な、澄んだ歯切れの良い音だけを出そうとする傾向があるように思います。
調律学校を卒業して間もない頃の私もそうでした。
一方ヨーロッパで伝統的に行われている調整・調律を施したピアノには、付帯音がたくさんあり、
日本ではその付帯音をいかに無くし、ピュアな音色に仕上げるかに重きが置かれます。
求める音色の方向性が、全く異なるのです。
さらに、“音色の変化を可能にする”という点においても、日本とヨーロッパの調律は大きく異なります。
ヨーロッパの調律では、指の腹を使ってそっと鳴らすと「オー」や「ウー」と少し閉じ気味の声も出ますし、
手首を徐々に上げいくと「アー」と喉がリラックスした声も出てきます。
ところが日本の調律では、先に申し述べましたとおり、母音の変化をつけることができないため、
弾き方による音色の変化を出すことはできません。
これは、両文化の根本的な違いを表しているのではないかと思います。
絵画という芸術を例にとってみます。
西洋では、白い画面いっぱいに、色とりどりの絵の具を乗せて、色の変化で表現しようとします。
一方日本では、白黒の濃淡だけで表現する墨絵の文化でした。
また、何もない白い部分をいかに表現するかに重きが置かれるなど、「間を楽しむ」のも日本独特の文化といえるでしょう。
ピアノにおける「音色」についても、同様の文化が存在するのではないかと思います。
西洋では、音色も様々に変化するべきと考え、日本では音色は濃淡であると考えられているのではないでしょうか。
こう考えれば、両者のピアノ調律の違いにも納得できます。
ヨーロッパスタイルの調律を施すと、実際、倍音はうなって聞こえますが、
それ以上に基音がしっかりと太く出ていて、基音そのものはうなっていません。
それどころか、ハーモニーを弾くと、コーラスのようにまっすぐと美しく伸びていき、
実に気持ちの良い音色が空間全体に広がっていきます。
残念なことに日本の調律に慣れてしまった調律師には、このヨーロッパの伝統的な調律はなかなか受け入れてもらえません。
その要因として、まずは日本の住環境、次に日本の言語が関係しているのではないかと考えられます。
湿度の高い日本では、住居には障子や畳、ふすまや土壁という、湿気を吸収する素材が使われてきました。
これらの素材は、湿気とともに音も吸収します。
このような響きのない住環境の中で生まれ育ったのが、日本の伝統楽器である三味線や琴、尺八です。
音が吸収される中でも「ペンー」とアタック音が小気味良く鳴り、
鳴った後の静寂の中で「間」という付加価値を生み出す、日本が誇る素晴らしい楽器です。
一方西洋音楽は、石造りの教会や宮殿など、響きのある環境の中で生まれ育ちました。
音の頭だけではなく、伸びた後の音やハーモニー感も大切にされ、
今もその伝統が楽器や音楽芸術の中で受け継がれています。
さらに、音楽と密接な関わりを持つといわれる言語という側面からもお話したいと思います。
日本語は発音のバリエーションが少ない言語で、母音は「あいうえお」の5つしか存在しません。
一方ヨーロッパの言語では、母音は10以上あり、子音、母音ともにバリエーションも豊富です。
巻き舌や喉を震わせるRや、Ch(カとハの同時音)のような微妙な発音の子音も存在します。
このことが日本人調律師にどのように影響するか、もうおわかりでしょうか。
ヨーロッパスタイルの調律を施されたピアノから聴き覚えのない発音、すなわちRやChの付帯音が出てくると、
ほとんどの日本人調律師は、それを「濁音」と感じてしまいます。
そして、その濁音を排除してピュアにしようと躍起になってしまうのです。
一見濁音と思われる音の中に、重要な音の成分を聴き取ることができないのです。
私は若い頃にイスラエルで生活し、キブツという集団に属し現地の人たちと寝食を共にする中でヘブライ語を習得しました。
ヘブライ語には、非常に微妙な発音が多く存在します。
そういった聴きなれない様々な発音や付帯音に接してきた経験が、
調律師として日本人の感覚から一歩踏み出す上で大きな役割を果たしたのではないかと感じています。
初めて当店に調律を依頼されたお客様は、皆様大変驚かれます。
「別のピアノになったみたい!」と、口をそろえて言われます。
ピアノを変えたわけでも何でもなく、
私たちはただ、ヨーロッパの伝統に基づいた技術をもって、ピアノ本来が持つ“本当の声”を引き出しているだけなのです。
ピアノは西洋で生まれ育った楽器であり、西洋音楽を奏でるための楽器です。
私共は、ヨーロッパの伝統的な技術でもってピアノを調整・調律致しております。
西洋音楽で求められる本場ヨーロッパの響きを、より多くの皆様に楽しんで頂けますよう願っております。
遠方にお住まいの方も、是非一度、ヨーロッパスタイルの調律を体験してみてください。
|